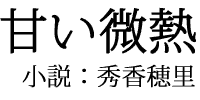

「んー、まだちょっと熱があるみたいだなぁ」
俺が差し出した体温計を見て、亮一さんがふっと顔を曇らせた。
「すみません。せっかく、みんなで予定立てたのに……」
声が掠れて咳き込むと、ヒロと太陽が毛布を顎まで引っ張り上げてくれた。
「明日叶ちん、ムリしないで。風邪って、こじらせるとコワイんだから」
「そっスよ! 明日叶センパイだけの体じゃねえんスから、大事にしてください」
「なんだったらコイツにうつしていいから。どうせバカは風邪ひかないっていうし」
「うっ……た、確かにカゼひいたことねーけどさ……」
いつもよりも声を落とした太陽とヒロの横から、桐生さんと眞鳥さん、興さんが代わる代わるのぞき込んできた。
「ここのところ毎日、寒いですからねえ。明日叶、薄着だし」
「インフルエンザではないと診断されたのだから、安静にしていれば落ち着くだろう」
「あすか、くすり、苦いけど、ちゃんと飲むんだぞ?」
「気を遣わせてしまって、すみません……ごほっ」
普段通りに話そうとしても、やっぱり咳に邪魔される。
「明日叶、無理に話さなくていい」
「うん……」
気遣わしげな顔の慧に、俺はなんとか頷き返した。その熱っぽい額を、大きな手がそっと覆う。ディオだ。
乾いた手はいつもよりもひんやりと感じて、気持ちがいい。
その感触にほっと息をついた俺に微笑んだディオが、みんなをぐるっと見回す。
「……で? どうする、今日の予定は」
晴れた日曜日の今日、チームグリフのメンバー全員で、遊びに行くはずだった。
休日に、みんなで遊びに行くというのはわりとめずらしい。
普段から一緒に行動していることもあって、休みの日は各人が自由に過ごすことがほとんどだ。
でも、少し前、この魁堂学園近くのスケートリンクがオープンしたことを知った亮一さんが、ミーティングの終わりかけに、『たまには、みんなで遊ぼうか』と言い出したのだ。
『休みの日にみんなで一緒になんかするって、あまりないだろ? ミッション以外での親交を深めるっていうのも大事だよ』
『えーっ、せっかくの休みなのに全員行動〜!? ウッザー……。第一、寒いしー、メンドーなんですけど』
『オレもスケートなんて嫌ですよぅ。なんでワザワザそんな寒いとこに行かなきゃなんないんですか』
『オレ、行きたいっス!! だって面白そうじゃん! ね、兄貴も行くっスよね?』
消極的な眞鳥さんたちを尻目に、ハイハイハイ、と威勢よく手を挙げた太陽がディオに迫る。それに鷹揚に頷いて、ディオが俺を振り返った。
『いいぜ。明日叶も行くだろう?』
『うん、スケートなんて久しぶりだから行きたい』
『なんだよー、明日叶ちんが行くって言うならボクだって行くよー!』
『小学校のレクリエーションか。あいつらのレベル的にはスケート程度がちょうど良いかもしれないな』
『レクリエーションなら暖かいとこに行きましょうよ〜。温泉とか』
『おまえは年寄りか』
『まあまあ、桐生も眞鳥もそんなこと言わずにさ……。藤ヶ谷はどう? 興は?』
『俺は、明日叶が行きたいなら行く』
『……うむ。つまんなかったら、寝る、かも』
『興ちゃん、スケートリンクで寝たら凍死しちゃうよ?』
『よし、じゃあ、みんなで行こう』
なんのかんの言いつつ、全員、この日は予定を空けていた。
もちろん、俺も楽しみにしていた。グリフのみんなで遊びに行くなんて、めったにないことだから。
でも、一昨日あたりからなんだか背筋がぞくぞくすると思っていたら、あっという間に熱を出してしまった。
幼い頃ならともかく、いまは毎日トレーニングで身体を鍛えているから、めったなことじゃ体調を崩さない。次のミッションはもう少し先だから、ちょっと油断してたんだろうか。
「明日叶をひとり置いていくのは心配だなぁ……」
頭をかく亮一さんに、眞鳥さんや慧が同意する。
「今日はやめといて、また別の日にしてもいいんじゃないですかぁ? スケートじゃなくてもいいわけですし」
「明日叶が行かないなら、俺も行かない」
「そッすよね。やっぱ、センパイのカラダが心配だし……」

「あの、俺は大丈夫ですから」
慧の断言にしょんぼりと肩を落とした太陽を見て、慌てて遮った。
来週からは、次のミッションの準備が始まる。そうなったら、みんなで遊ぶというのも当面お預けになってしまう。
「俺に構わず、遊びに行ってきてください。風邪を引いたのは俺の責任です。昨日より熱が下がったから、今日一日寝てれば治ります」
俺のせいで、忙しいメンバーがせっかく合わせてくれた予定を台無しにしてしまうのは嫌だ。心配してくれるのはほんとうに嬉しいけど……、でも。
言い切ったところで、ディオとちらっと目が合った。かすかな目くばせに、ディオが頷く。

「明日叶がああ言ってるんだし、滑りに行こうぜ」
視線の意図を正確に読み取って、ディオがそう言ってくれる。
「ここで俺たちがいつまでも騒いでたら、こいつだって眠れないだろ」
その言葉に、集まったみんなが顔を見合わせた。
「正論だな」
「じゃあ、俺たちは出かけるけど、ちょっとでも具合が悪くなったら我慢しないですぐに校医を呼ぶんだよ。俺たちも早めに帰ってくるから」
「ゆっくり寝ときなさいね〜」
「明日叶ちん、おみやげ楽しみしててね!」
「はい、行ってらっしゃい」
ひらひらと手を振る眞鳥さん、眼鏡を押し上げてため息をつく桐生さんや興さん、ヒロ、みんなの背中を押して、最後に部屋を出ていこうとしたディオがくるっと踵を返して戻ってきた。
「あ、……ディオ?」
なんだろう。忘れ物でもしたんだろうか。
毛布の縁からあたりを見回す俺に、ディオがかがみ込んできて、くしゃりと髪を撫でてきた。
「早く治せよ。おまえが元気じゃねえと落ち着かないぜ」
俺のことを覗き込んでくる目は、さっきまでと違う。チームメイトでも、ただの同級生でもない――俺だけに向けてくれるディオの眼差しだ。とても大切なものを見つめるような深い視線に、胸の奥がきゅうっと引きつれるように甘く痛む。
「……わかってる」
ディオの気障なセリフやスマートな振る舞いには少しずつ慣れてきたけれど、こういう不意打ちみたいに見せてくる優しさには、どうしてもこころが追いつかない。もごもごと呟いて毛布を引き上げた仕草がおかしいのか、ディオが笑う。
「おまえも、俺のそばにいられないのはさみしいだろ?」
そう言いながら、ディオが髪をかきあげて、額にキスをしてきた。汗ばんだ肌を味わうように、舌先で軽く舐められると、違う熱が出そうになる。
「やめろよ。そんなことしたら……」
「ん?」
「……熱があがる、だろ」
照れ隠しに、ゲンコツをつくってディオの頬に軽くあてた。
「可愛いこと言ってんじゃねえよ、ガッティーノ。食うぞ?」
「バカ、ふざけたこと言ってないで、早くみんなと行ってこいよ」
「ふふ、そうやって意地を張ってるうちは大丈夫だな。じゃあ、明日叶。また、あとで」
「うん、……また、あとで」
鼻先を軽く人差し指で弾かれ、互いに笑った。
髪先をもう一度優しく引っ張られて、その感触が消えないうちに、ぱたんと扉が閉じて、賑やかな声は少しずつ遠ざかっていった。

「はぁ……」
ため息をついて、天井を見上げた。カーテン越しに冬の弱い光が差し込んで、窓に明るい模様を描いている。
「もう、みんなスケート場に着いた頃かな……」
ディオたちが部屋を出ていってから、もう三十分は過ぎただろうか。
ひとりになるとやけに部屋を広く感じるのは、やっぱり、風邪を引いたせいかもしれない。身体が思うように動かないと気まで弱くなってしまうし、重く熱い頭はなんだか同じようなことをぐるぐると考えてしまう。
ちいさい頃の俺はちょっとしたことで熱を出しやすくて、よくこうしてベッドでひとり眠っていた。熱に浮かされた浅い眠りから目が覚めると、世界でひとりぼっちになってしまったような錯覚に陥って、心細くて仕方なかった。
午前の光が差し込む静かな部屋でひとり寝ていると、そんなことを思い出す。
もちろん、いまは誰かがそばにいないと心細いほど、子どもじゃないけれど。
「退屈だな……」
考えてみれば、この学園に来てから、こんなふうにひとりぼっちの時間をもてあますことはほとんどなかった気がする。訓練で忙しかったり、ミッションのことで頭がいっぱいだったり、それから――いつだって、ディオと一緒にいたし。
そういえば、このベッドでひとりで寝るのだって、ほんとうにひさしぶりだ。
「だから、部屋が広く感じるのか……」
いつもふたりでいる空間にひとりきりだから、こんな妙な気分になるんだろう。
余計なことを考えるくらいならば眠ってしまえと目を閉じるけれど、明るすぎるせいか、上手く寝付けない。
「……俺も、スケートに行きたかったな」
「じゃあ、今度一緒に行こうぜ」
かすかな声で呟いたはずなのに、予想外の応えが返ってくる。振り向けば、開いた扉からディオが顔をのぞかせていた。
「ディオ! どうしたんだよ、スケートに行ったはずじゃ……」
「起きるな。寝てろ」
起きかけた俺をベッドに押し戻し、ディオが椅子を引っ張ってきてどかりと腰掛けた。
「またあとで、ってさっき言っただろ」
「言ったけど、こんなに早く戻ってくるって思わなかった」
口では反発したけど、目がどうしてもディオを追いかけてしまう。
みんなと一緒に遊びに行ったほうがディオだって絶対に楽しいはずなのに、俺のことを気にして、戻ってきてくれたんだ。
申し訳ない気持ちと嬉しさが混ざり合って、どんな顔をしていいかわからない。
「寝てれば、すぐに治るのに。俺のこと、そんなに甘やかすな」
「甘えるのは病人と恋人の特権だぜ、ガッティーノ。それにな。じゃんけんで俺が負けたんだよ」
「じゃんけん……?」
なんのことだかわからなくて首を傾げた。
「あいつら、やっぱ、おまえが心配でしょうがないらしくてさ。誰かひとりはそばにいるべきだってうるせえんだよ。それで、じゃんけんで一番負けた奴が、おまえのところに戻るって話になったんだ。――で、負けたのが、俺」
「ディオが負けたのか……」
「いいだろ、べつに負けたって。それより、俺に看病されるのは嫌なのか?」
「そういうんじゃないけど」
「じゃあ、看病されとけよ。それとも……」
からかうように目が細められ、すうっと耳元に顔が寄せられる。そのまま流し込むように囁かれるのは、低い笑い声。
「エロいことされるんじゃねえかって期待してんのか、明日叶は」
「ば……っ! してるわけ、ない……っ!」
慌てて身をよじり、くちびるを噛み締めて睨みつけると、急な動きに咳が込み上げてきた。ケホケホと咳き込むと、ディオが背中をさすってくれる。
「ほーら、暴れるからだぜ? おとなしくしてろって」
誰のせいで暴れたんだ。そう言い返してやりたかったけれど、咳のせいでしゃべることもできない。
咳のあいだじゅう、ディオはずっと静かに背中をさすってくれていた。
余計なことをしたな、とそのちょっと眉をしかめた顔が語っている。そんな表情を見たら、それ以上言い返す気にはなれなかった。
「ありがとう……もう平気だ」
しばらくすると、ようやく咳が治まった。ぐったりと寝そべると、毛布をかけ直してくれたディオが、俺の息が整うのを見計らって声をかけてきた。
「ちょっと口、開けてみろ」
「うん」
親指と人差し指で顎を掴まれ、口を開いた。
「あー、まだ喉の奥が炎症を起こしてるみたいだな」
言いながら、ディオが小さな瓶をポケットから取り出した。蓋をねじ開けると、甘く濃厚な香りが鼻先をくすぐる。
「……はちみつ?」
「そう。咳が出るときは、これがいいんだよ。喉の炎症が治まる。騙されたと思って、試してみな?」
そう言ってディオは瓶に指を突っ込んだ。そのまま、黄金色のはちみつを指に絡める。
「ほら、舐めろよ」
その指先を、俺はじっと見つめ返した。舐めるって……この指を、だろうか。
「……机の引き出しに、スプーンがあるけど」
「面倒くせえよ。このままだと、シーツに垂れるぞ? ほら、あーん、してみな。あーん」
「子ども扱い、するなよ」
「してねえって。マジで、おまえを心配してるだけだ。のど飴みたいなもんだよ」
ほら早く、とうながす声に渋々と口を開けた。
くちびるの隙間に、ぬるりとディオの指が入ってくると同時に、甘いはちみつの香りと味が口内に広がった。じわりと唾液が滲み出てくるのを、思わず飲み下す。横たわった身体中に甘さがじわりと染みこむようだ。
ゴクリと喉が動くのを、ディオがじっと見ているのがわかる。
それがなんだか恥ずかしくて、目が合わせられない。
ゆっくりと丁寧に、頬の粘膜へとすりつけるように、はちみつが塗り込まれる。その甘さに唾液が溢れてきて、何度も何度も唾を飲み下した。そのたび、静かな部屋に嚥下の音が響くようで、恥ずかしさに顔が赤くなっていく。
ディオの硬く長い指が、咳き込ませないように慎重な動きで、口の中をなぞる。
「熱があるな……。熱い」
そんな囁きに、動悸が高まってしまう。甘すぎるはちみつのせいか、ひどく喉が渇いていた。何度も何度も、唾を飲み込む。覗き込んでくるディオの髪が頬に触れる。
キスをされるのか、と思わず目をつぶったけれど、それ以上のことはされなかった。
そろそろと瞼を開けると、俺のくちびるから引き抜いた指を、ディオが見せつけるように舌を伸ばして舐めるのが視界に飛び込んできた。

赤く、厚い舌が、唾液とはちみつでトロリと濡れた指を、ゆっくりとなぞっていく。
目を離すこともできず、声も出せず、ただその動きに支配される。
ディオが濡れた指で軽くくちびるに触れてきて、ようやく止めていた息を吐き出した。
「甘いな」

「……甘すぎる」
ディオの表情は平然としたもので、ひとりで興奮しかかった自分がバカみたいだ。憮然として、ぶっきらぼうな返事をしたけれど、ディオは楽しそうな笑みを崩さない。
でも、確かに息苦しさは少し薄れたみたいで、前より喉は楽になっていた。
そう言うと、ディオは当然だと頷いた。聞けば、ディオの実家では昔からは咳止めにははちみつ、というのがセオリーらしい。民間療法だが、意外に効くだろう? というディオの言葉はほんとうだったんだ。
「なに疑ってんだよ、明日叶」
「だって……ディオが、ちゃんと看病してくれるとは思わなかったから」
「ずいぶんな言いようだな。弱ってるおまえにつけ込んでエロいことをするとでも思ったか?」
「ちょっと……思った」
「俺は紳士なんだよ。病気につけ込むなんて、卑怯なマネはしない」
「嘘つけ。詐欺師のくせに」
「いまさら言うなよ。それに、つまんねえじゃねえか。風邪引いてんだから、いつもと違うプレイをしようぜ? とことん優しくしてやるよ、明日叶。弱ってるお前にかしずいて、お姫様のように大切に扱ってやる」
「……いい。遠慮する」
「じゃあ、早く元気になれよ」
ちいさな笑い声を立てながら、ディオが額にくちづけてきた。
いつもよりずっと、温かいキス。恋人だけがしてくれる、熱のこもった甘いくちづけだ。
俺を気遣ってくれることがわかるキスがくすぐったくて、嬉しくて、俺も釣られて口元をほころばせてしまった。
「……ディオ、ありがとう」
すんなりと礼が言えたのは、やっぱり熱のせいかもしれない。
そんな俺にディオはちょっと目を瞠り、さらに身を乗り出してきた。

「めずらしく素直だな、ガッティーノ。可愛いぜ?」
もう一度、くちびるが触れる。そのまま舌で軽く舐められて、首を振った。
「ダメだ。風邪がうつるだろ」
「熱をガツンと出せば治るっていうのが定説じゃねえか」
「無理言うなよ。いまは微熱まで下がったけど、この風邪、結構つらいんだぞ。咳がなかなか止まらないし。ディオにうつすのは……嫌だ」
「おまえの熱なら、苦しくても味わいたいんだがな」
そう言いながらも、ディオはあっさり引いてくれた。俺が普段より弱っていて、ろくに言い合いもできないことがわかったからかもしれない。
「でも、そばにいるぐらい、いいだろ?」
「……うん」
ディオの声に頷いた。
毛布の中にごそごそもぐり込んできた骨っぽい手が、俺の手を探り当てて掴む。
「やっぱり、いつもより手が熱いな」
指を絡めるように俺の手をゆっくりと握り締め、全身のだるい感覚をやわらげるように揉みほぐしてくれるディオと目が合うと、このまま眠ってしまいたいほどの安心感に包まれる。
さっきまでがらんとしていただけの部屋が、いまはとても心地よく感じられる。
ただディオがいるだけで、こうやって手を握ってくれるだけで、心細さや、さみしさや、そんな弱った気持ちが、ひとつひとつ、丁寧に、温かくとかされていく。
「眠るか? それともなんか欲しい物、あるか?」
「……少し喉が渇いた。飲み物が欲しい」
穏やかな声が降ってくる。甘やかすようなその声色にそそのかされて、ついねだってしまう。
「ああ、そういや、おまえに差し入れを預かってきたんだ」
ディオが、ジャケットのポケットからちいさな紙パックに入ったリンゴジュースを取り出し、手渡してくれた。
「あ、これ……慧からだろ? 覚えててくれたんだ、あいつ」
「おまえ、これが好きなんだってな」
「うん。俺、ちいさい頃はよく熱を出すほうだったんだ。慧とは幼馴染みだから、俺が学校を休むと、リンゴジュースをうちまで届けてくれたんだ。懐かしいな……」
「――……へえ?」
受け取ると、ディオが空いた手で器用にストローを差してくれた。片手を握られたまま起き上がり、一口飲むと、さっきのはちみつと混ざって、懐かしい味がした。
「慧の家になったリンゴで、おばさんが作ってくれたリンゴジュースは冷たくて甘くて、すごく美味しかった。慧は、それを飲んで早く元気になれって、学校に来るのを待ってるって言ってくれて……あ」
不意に、俺の手を掴むディオの手に、ぐいっと力が入った。痛いほどの力に驚くと、ディオはしかめ面をしている。
「……どうしたんだ、ディオ?」
問いかけに返ってきたのは、深い深いため息。
「明日叶、いま、おまえの前にいる男は誰だ?」
「……ディオ、……だけど」
「そうだ。おまえの男は、俺だよな」
断言されて、頬がカッと熱くなる。
ディオの言葉に隠された意味がわかるから、慌てて毛布の中に隠れようとしたが、一歩遅かった。
「前言撤回だ。お前を甘やかすと、ろくなことがない」
「え、え……っ、うわ、ディオ!?」
ジャケットを素早く脱ぎ捨てたディオが、強引にベッドにもぐり込んできて覆い被さってきた。
「優しくされるのは遠慮するって言ったよな、明日叶。じゃあ、メチャクチャに犯してやる」

いまにもくちびるが触れそうな距離で囁かれたその艶めく声を、俺は夢でも聞くような気がする。きっとこの先、何度も、思い出してしまう。
ディオだけが発することができる、強い力と熱がこもる声を。
「今度、おまえが風邪を引いて寝込んだときに真っ先に思い出す記憶を、俺がつくってやるよ」
「ディオ! ちょ、ちょ……っと、待て、って……さっきの話は、昔を思い出した、だけで……っ」
「だったら、いま、おまえを抱き締めてる男のことをきっちり胸に刻んで、それだけを思い出すようにしろ」
無茶なことを言う大きな影が一層濃くなり、抱きすくめてくる。広い胸を押しのけようとした手首すら掴まれ、押さえ込まれて動けない。
「おまえの身体のことは、俺が一番よく知ってる。……安心しろ。無茶はしねえよ」
「――ディオ……」
「甘い甘い思い出にしてやるぜ?」
笑い混じりの熱い吐息でくちびるを優しくふさがれることに、俺は、もう、抗わなかった。

「慧、昨日はリンゴジュース、ありがとう。おかげで風邪、治ったよ」
「そうか、よかったな」
翌日、一般教養教室で顔を合わせた慧に礼を言うと、安心したような笑顔が返ってきた。でも、すぐにいつもの無表情に戻る。
「あいつはどうした?」
「あいつ? あ、……ああ、ディオは、うん、……その、風邪、引いたみたいで、今日は休むって」
「……あいつに、うつったのか?」
ディオに風邪がうつすようなことをしてしまった昨日のことを思い出して、治った風邪がぶり返すように顔が火照ってくる。
あのあとも、たくさんはちみつを舐めさせられて、喉もすっかりよくなったけど、ベタベタのシーツを取り替えたり、俺の汗を拭いたりしているうちに、ディオはすっかり身体を冷やしてしまったらしい。めずらしく俺を抱き枕にしないで自分の部屋に戻っていったと思ったら、朝にはすっかり病人になっていた。
「みんなとのじゃんけんにも負けるし、俺の風邪はうつされるし、ディオにとっては災難だったかもな」
「じゃんけん?」
慧が不思議そうに、眉を寄せた。あれ、慧は参加してないのか……?
「みんなでじゃんけんして負けたから、ディオが看病に来たんだろ?」
「俺たちは、じゃんけんなんかしてない」
「え?」
わけがわからない俺に、慧が説明してくれた。
俺の部屋から出たあと、みんなで寮を出てバスを待っていたあいだ、ディオがやっぱり看病に戻ると言い出したらしい。
「明日叶を看病したい気持ちはみんな同じだ。でも、そんなことをしたら明日叶が気にするから、誰かひとりで十分だという、あいつの意見にも賛成だった」
「そうだったんだ……」
「それに、明日叶のそばにいられるのは『恋人の特権だ』と」
「……それ、ディオが言ったのか」
「ああ」
頷く慧に、顔が赤くなる。
人前で平気でそういうことを言うのは、いつものディオだけど……、やっぱりどうしようもなく恥ずかしい。しかも、ただ恥ずかしいだけじゃなくて、嬉しくもあるから困る。
じゃんけんで負けて看病にきたっていうのは、嘘だったんだ。ディオがスケートに行かなかったと知ったら、俺が気にすると思ったんだろう。
嘘つきなディオ。俺のことを素直じゃないっておまえはよく言うけど、おまえだって全然素直なんかじゃない。
「不本意だが、今回は譲ってやった。お前がいま一番そばにいて欲しいのは、あいつだと思ったから」
「慧……」
「あいつの看病にいくなら、……これを持っていけ」
慧に手渡されたのは、リンゴジュースの缶だ。
……もしかして、これ、俺が治るまで届けてくれるつもりだったのかな。
「ありがとう、ディオに渡すよ」
微笑んで、俺は甘酸っぱいリンゴジュースを受け取った。
昼休み、俺は寮へと向かっていた。
通り過ぎる学生たちが、大荷物を抱えている俺に目を丸くする。
気遣ってくれたのは、慧だけじゃない。太陽も、亮一さんも、みんな、ディオが休みだと知ると心配して、いろいろなものを持たせてくれた。
いまごろ、ディオは眠っているだろうか。熱のせいでつらいだろうか。昨日の俺みたいにぼんやり天井を眺めているだろうか。
この見舞いの品々を目にしたら、ディオはどんな顔をするんだろう?
みんなが案じていることを鼻で笑うかもしれないし、『どうでもいい』なんて突き放すかもしれない。
でも、ディオ、俺だって心配してるんだ。風邪をうつしてしまって悪いと思ってるし、早く元気になってほしい。
もとはといえば、ディオが無茶をしなければこんなことにはならなかったんだけど……。
しかめ面をすべきか、笑うべきかわからないまま、ディオの部屋の前に立った。あたりはしんと静まり返っている。
どうしようか。
ちょっと考えをめぐらせ、大荷物をなんとか左手に持ち替えて、扉をノックした。
「ディオ、俺だよ。起きてるか?」
「……明日叶か? 入れよ」
いつになく掠れた声を扉越しに聞いて、決めた。
素っ気なくあしらうことはしない。怒ることも、嘲笑うことも、しない。
風邪を引いているからキスはしてあげられないけど、大切にしよう。
いまの俺にできる精一杯のことを、ディオに。
こんなときじゃなければ、なんでもひとりで完璧にこなせてしまうディオの世話なんてできないだろうし。
――おまえがしてほしいって思うことを、全部叶えられるかどうかわからないけど、俺は俺なりに、なんとかしてみせるから。
「見舞いに来たんだ、ディオ。具合、どうだ?」
不謹慎かもしれないけど、満たされた気持ちで微笑みながら、午後の光が射し込むディオの部屋の扉を開けた。



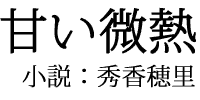

 「あの、俺は大丈夫ですから」
「あの、俺は大丈夫ですから」 「明日叶がああ言ってるんだし、滑りに行こうぜ」
「明日叶がああ言ってるんだし、滑りに行こうぜ」 「はぁ……」
「はぁ……」 赤く、厚い舌が、唾液とはちみつでトロリと濡れた指を、ゆっくりとなぞっていく。
赤く、厚い舌が、唾液とはちみつでトロリと濡れた指を、ゆっくりとなぞっていく。 「……甘すぎる」
「……甘すぎる」 「めずらしく素直だな、ガッティーノ。可愛いぜ?」
「めずらしく素直だな、ガッティーノ。可愛いぜ?」 いまにもくちびるが触れそうな距離で囁かれたその艶めく声を、俺は夢でも聞くような気がする。きっとこの先、何度も、思い出してしまう。
いまにもくちびるが触れそうな距離で囁かれたその艶めく声を、俺は夢でも聞くような気がする。きっとこの先、何度も、思い出してしまう。
